
JOURNAL
Interview_04 :
UP DATE : 2021 / 02 / 22
自分の価値観、しっかりと
江藤公昭(パピエラボ店主)

INTRODUCTION
原宿駅から徒歩で7-8分、千駄ヶ谷小学校の交差点近くに店舗を構えるPAPIER LABO.(パピエラボ)。紙と紙にまつわる物を取り扱うお店。入口に立てば一目で見渡せる小さな店内。パサッと積み重なる端がボサボサとしている紙、なんだかインクが黒光りしている写真が印刷されたポストカード、額縁に収められた印刷物やポスター。ノート、ペン、ペン立て、靴下などなど、ほほぅ!と思う商品たちが並んでいる。パピエラボのディレクターを務める江藤公昭さん。彼にとってこのサイズ感がちょうどいいんだろう。取り扱うすべての商品にしっかりと目が行き届いている感じが安心する。商品が並ぶ棚の反対側にはカウンターがあって、その上にはほとんど何も置かれていない。必要があればここでアレヤコレヤとお客さんたちと打ち合わせをするのだろう。と、すべては僕の勝手な想像。オフセット印刷が主流になり、それまであった活版印刷が廃れてしまった現在だが、約10数年前にその活版印刷が見直されるきっかけのひとつを作ったのがパピエラボの江藤さんたち。紙や印刷を通して今感じていること聞きました。


江藤公昭
(PAPIER LABO.)
2007年、紙にまつわるプロダクトを取り扱うショップ、パピエラボを設立。世界から集めた紙やそれにまつわるプロダクトを取り扱う。その他デザイン、印刷物のディレクションなどもおこなう。
江藤さんはパピエラボをやる前はどんなことをされていたのですか?
江藤:ランドスケーププロダクツという会社でデザイナーとして働いていました。いろいろなことをやっている会社で、木製の家具を作ったり、他にもいろいろなプロダクトを作ったりしていました。カフェもやっているのでそのカフェの手伝いやら、とにかくやれることすべてをこなしていました。なので特に紙モノを専門に仕事をしていたわけではなかったんです。印刷物はいろいろなことをしている業務の一つでしかありませんでした。

そうなんですね、その中でどうして紙に目が向いたのですか?
江藤:タイミングでしたね。家具や雑貨の買い付けのために海外に行って、お店をまわりをしているときに活版印刷で作ったカードが置いてある店があったんです。そのときは活版なんて全然知らなくて。印刷物としてそれを見たときにとても面白いって思ったんです。その時、勝手にたくさん買い付けちゃって。お店でそれを置くようになったら、「これは活版印刷だね」って言ってくれるお客さんたちがいて。これって活版印刷なんだって思ったんです。今思えば、世界的にちょっとずつ活版印刷が再注目されつつあった時期でした。パピエラボをオープンしたのが2007年でその少し前、たしか2005年とか2006年くらいだったと思います。
当時はまだネットで印刷物の入稿とかも少ない時代でした。それに活版印刷所も一番廃れていた時期。印刷所をやっている人たちも高齢な方ばかりであとを継ぐ人もいなくて、たくさんの工場が廃業になっていました。当時の活版印刷所ってオープンな感じではないんですよね。職人さんが黙々と働いていて、なかなか入りにくい。入ってしまったらなにか頼まないといけない雰囲気ですし、お店ではないので接客されるわけでもないし。だからいきなり訪れるってすごいハードルが高いんです。興味があって作りたいって思って行っても、どうやって版を作ったらいいのか?どう入稿すればいいのか?とか。もちろんそういう場所ではパソコンで入稿なんてないですから、まったく発注のしかたもわからないような状況で。だからこそ面白いんじゃないかって思って。素材としてもですね。例えば今までだとオフセットのフラットな印刷だったら大して魅力を感じなかったと思うんですよね。活版になったときに、ちょっとふわっとした紙や古い紙、ざらっとした紙とかに印刷できて、その素材感が面白いなって思ったんです。活版以外でもできるんですが、すごく活版に向いているなと思って。

活版印刷だと、印刷した部分に凹凸ができますよね。
江藤:そうなんです。凹凸もできますしあとはインクの滲みもできるんです。一般的な印刷ですとそういう凹みや滲みはなくて、きれいに印刷されちゃうんです。当たり前なんですが。僕は逆にその部分が面白いと思って、職人さんのところに通い始めて少しずつやりとりをするようになったんです。これはみんな興味あるんじゃないかな?って思って。それから活版再生展という展覧会をやろうということになったんです。
最初は紙と活版がセットだった感じですか?
江藤:そうですね、そもそも初めは活版印刷というものを知らなかったので、紙はその印刷をするための「物」として面白いと思ったんです。もちろんグラフィックデザイナーの人たちも印刷方法の一つとして活版を知って、興味を持っている人たちもいました。入口が違う人たちがパラパラいて、そういう人たちが集まってもう一回活版印刷を盛り上げようという感じになりました。それが2007年くらいでしたね。
活版印刷所って町工場って言うほどでもない、住宅街にでもありそうなアルミの引き戸をカラカラって開けると、すぐそこで作業しているような場所ですよね。そういう印刷所にアプローチしたんですか?
江藤:そうです。ドアを開けるとちょっと怖そうなおじさんが作業している、みたいな下町の。僕はそういうところに行けないタイプなんです、ちょっと怖くて(笑)。なので「展覧会をやるので」という名目で訪れました。そうすれば職人さんたちもちょっとは興味を示してくれるというか。それでも「こんなの廃れた技術だから」って断る方もいました。「こんなの残してもしょうがない」って言う人がたくさんいたんです。自分たちの技術に価値があるって誰も思っていなかったんです。そんな中、「じゃあ、教えてあげるよ」って言ってくれる人もいたんですよね。そうやって面白そうな職人さんに声をかけたんです。当時の活版印刷って、印圧をかけるとが、業界ではタブーだったんです。紙にへこみを作るなんて下手な職人さんなんです。へこまさずに平らに印刷できる職人がうまい印刷とされていましたから。印圧をかけず、滲みも出さずに印刷することにこだわりを持ってやっている職人さんがほとんどでした。もちろんそれもとてもいいんですけれどね。
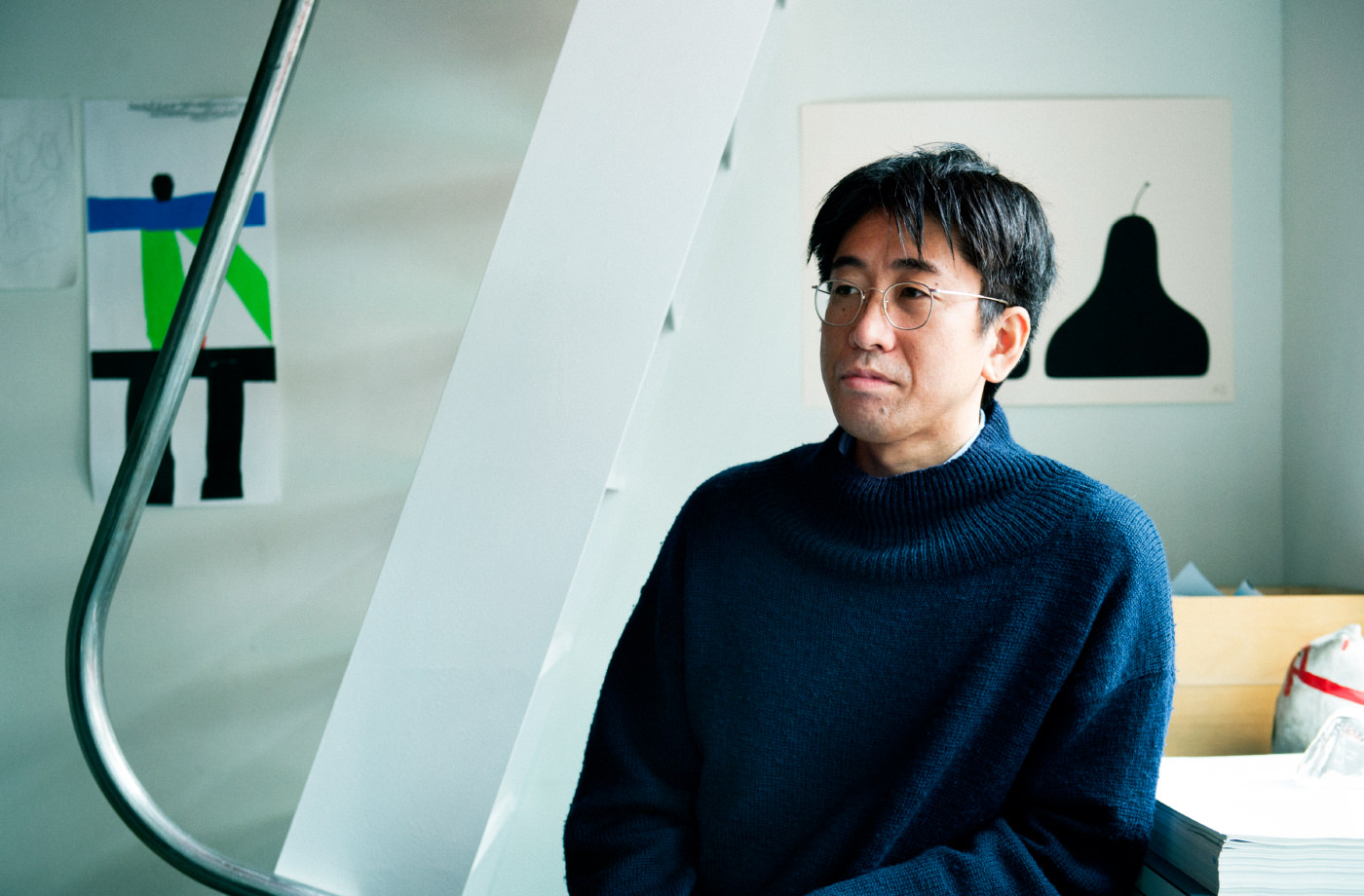
なるほど、そうなると江藤さんが惹かれた活版印刷って、今オフセット印刷があるからですか?
江藤:それはありますね。だから僕らが感じている魅力を、活版をずっとやっている人たちには気がついてもらえないんです。当たり前ですよね。ずっとやってきた印刷職人さんが技術を求めてやっていくと究極がオフセット印刷になってしまいますから。じゃあ活版の特徴を生かしてあえてへこましてしまおうという職人さんはいなかったんです。僕たちがそれを説明して、「面白い」って返してくれる職人さんと、まったく理解してくれない職人さんの両極端でした。腕がいい人に限って理解してもらえないんです。でも中には若い人たちが感じた面白さをわかってくれる人がいたり、文句言いながらもやってくれる人もいたりで。「こういうこともできるぞ」って教えてくれる人も出てきてディスカッションできるようになってきました。
その「活版再生展」とはどんな展示会だったんですか?
江藤:世田谷区の生活工房が企画したもので、僕はSAB LETTERPRESSという活版印刷のブランドをやっていた武井さんに誘われて参加しました。デザイナーさんや作家さんが自分の作品を活版で作って出展したり、当時世田谷の活版印刷所が廃業することを知って、その工場から活字や印刷機を一式移設したりしました。職人さんを呼んで、そこで印刷の体験できるようにもして、ワークショップあり展示ありみたいな感じで。若い人たちが参加して、見に来る人も若い世代の人たちがほとんど。新しい活版の解釈としてやりました。その展示で活版を知らなかった人たちにも認知してもらえるきっかけになった展示だったと思います。

パピエラボを始めたのは?
江藤:活版再生展でオールライトグラフィックスっていうデザイン事務所をやっていた高田さんと出会ったんです。彼も活版に興味を持ってくれていて。活版再生展は一ヶ月限定の展示だったんですが、それだけで終わってしまうのはもったいないって高田さんと話をしていて。当時所属していたランドスケーププロダクツの一階にあまり使われていない倉庫兼作業場があったんです。その場所を使ってお店にできないか?というのを会社に話して。それから一ヶ月でお店を作ったんです。それが初めてのパピエラボでした。
そのとき高田くんともうひとり、SAB LETTERPRESSの武井さんと三人で始めました。パピエラボが窓口になってオールライトに印刷物の発注をするというカタチでやっていました。僕たちがそうだったように、活版印刷所に直接頼むのって敷居が高いし、どんな紙を選んでいいのか?というのもわからない人もいるから。街中にお店があって、気軽に相談できる場所があるといいなと。お店だと気に入らなければ出ればいいし、話したくなければそのまま放っておいてくれるし、話だけ聞きたい人も聞けるし。そういうオープンなスペースが良かったんです。ちょっと考えてまた戻ってきてくる人もいますしね。
そう考えると昔はどうやって活版印刷所に名刺とかオーダーしていたんでしょうね?
江藤:そうですよね、たぶん名前とか必要な情報を書いた原稿を職人さんに渡して。活字の場合、文字が明朝かゴシックくらいしかないので。サイズも数パターンしかないですし。あとはインクの色くらいで。頼む方も作る方もあまり細かくはなかったんじゃないかなと思います。それが当たり前で。逆に僕らが細かく言って、活字をそのまま組んでもらってもちょっと文字間(文字と文字の間隔)がおかしかったりするんです。そうすると活字と活字の間に紙を挟んでその間隔を調整してもらうんですけれど。面倒な作業なので露骨に嫌がられることもありますが、やっぱり綺麗に仕上がったのを見ると満足そうな顔をしてくれます。
こうしてお話しを伺っていると活版を通して紙の魅力を知ったというところが大きいようですね。
江藤:それは大きかったですね。今まで印刷できないって思っていた紙に相性良く印刷できたんです。活版と紙の相性っていいなと思って。今まで使えないって思っていた紙がこうやって使えるんだ!って。それを印刷方法を通して知りましたね。活版印刷のために紙を探すことはあまりしていませんが、骨董市とかで古い紙をみつけると、これに印刷したら面白いかな?とは思ってしまいますね。
こうやって活版、活版と言っていますけれど、僕は飽き性なので、始めた当初はすぐに飽きちゃうだろうと思っていました。レタープレスラボ、みたいな名前ではなくてパピエラボにしたのも、もう少し広い範囲でいろいろできるようにしたかったから。プロダクトも好きだし、ちょっとした逃げ道ですね。活版はあくまでも印刷手段の一つとして。それだけが目的にはしたくなかったんです。初めはペーパーラボという名前にしようと思ったんですが、そういうお店が既に他にあったので(笑)。

パピエラボは紙をメインに扱っているお店ですが、紙をどのように広げていこうと思っていますか?
江藤:「紙にまつわる物」と言うことでやっているので、例えばカードスタンドだったり、ペンだったりそういう物も扱っているんです。ちょっと強引な物もありますけど。紙大好き、活版大好きという感じをあまり出したくなくて。僕自身、ファッションも好きですし、他の素材も好きです。たまたま表現方法が紙だっただけなんです。でもマニアの方が来ても困らないくらいの知識はあります。さっき表現方法のひとつといいましたが頻繁に印刷所に通っていますし、そこはちゃんと持っておきたい。その上でそれが前に出すぎないようにしています。
紙っていろいろなことができると思います。絵を描いたり、印刷したり、加工したり。アーティストの人たちと一緒に作ったりもしていますね。
江藤:そうなんです。みんなが使いたい紙をヒアリングして。それに適した紙を提案したり、印刷方法もそうです。ガラス作家のである山野陽子さんが作品を作る前に描いたドローイングが素敵でその絵を印刷した物を商品にしたり。写真家の三部正博さん、鈴木理策さん、志賀理江子さん、菅原一剛さんと一緒にコロタイプ印刷という方法で写真のポストカードも作りました。世界最古の印刷技術なんです。京都にある便利堂という美術印刷や出版の老舗の印刷屋さんでプリントをお願いしました。日本ではここでしかできないんです。とても高額なんです。お店で販売もしています。他にも三部さんの写真を活版印刷でプリントしたフォトカードもあります。活版で網点を作って、それを5版重ねてプリントしてあります。油がどっしりと紙にのった質感なんです。印刷して乾かしてを5回繰り返すので、完成させるのに1週間かかるんですよ。なので年に一度くらいしかできないんです。

いろいろなプリント方法をやっているんですね。日本には和紙があるように、国によって紙の特徴ってあるんですか?
江藤:あります。日本と韓国は構造も作り方も同じなんですが、でもやっぱり違うんですよね、張りだったりとか。和紙の中でも違いがあるのと同じように。インドですとコットンペーバーとかがありますね。使わなくなったコットン、たとえばTシャツとかを砕いて、日本の和紙とかと近い方法で漉いて作るんです。このお店でもインドで作ってもらった紙があるんです。ざらざらの質感で均一性もないですし表面もボコボコしています。これ、日本だったら完全にB品扱いなんです。こんな製紙メーカーが日本にあったら一瞬で倒産していると思います。なのでこの感じの紙は日本では作りづらいんですよね。だからインドで作ってもらっているんです。

そう考えると、人それぞれの価値観ですね。ゴミ同然と思う人もいれば、コレがいいという人もいる。
江藤:そうなんです。日本の人は品質に対してとても繊細ですから。その他にも紙糸を使った靴下も扱っています。紙糸とコットンを編み込んで作ってあるんです。お店ではアメリカ、台湾、韓国、スイス、インド、ドイツ、日本、七カ国くらいの紙を扱っています。
紙は濡れるとふやけてしまいますし、力を入れるとすぐに破れてしまいます。その反面、すごく長く持つ素材でもありますよね。再生できたりもするし。
江藤:仕事をしていて再生紙やFSC認証をとっている紙を使いたいと特に最近よく言われるんです。FSC認証って環境に配慮した物かを認証制度です。再生紙を何パーセント使っているとか。そういうのもいい活動だなって思うし、地球がこれだけ汚れてきて、なにもかも新しく作るのって絶対に良くない。ただ一方でそれがまた活版印刷とかと同じような感じですけれど、再生紙がすべていいという風潮もなんだかちょっと違うなと。再生紙でもいい紙は使いたいですが、好みじゃない物もあってそういうのはもちろん使いたくないですね。再生紙を使うということが目的になってしまうようなことには興味がないんです。いいなと思った紙が再生紙だったらいいですよね。そういうバランスかなって思います。

自分が気に入った物をしっかり選んで使うことって大切ですね。すぐに破いて捨ててしまう物を作るより。例えばいい名刺をもらうと捨てられないですよね。ぶっちゃけ、名刺交換しなくていい時ってよくありますよね。カタチだけの。なんか携帯でピッってできた方がいいなって思うときありますよね。
江藤:ありますね。活版でいい名刺作るとそこそこいい値段しますし(笑)。名刺を作りに来る人たちにもそう言っちゃいますね。形式的な交換だけする人たちにはいくら渡しても伝わらないし、お金がもったいないのでオフセットでいいと思います、って伝えます。とは言え、伝わる人にはしっかり伝わりますし、とっておきたいって思いますしね。
社会ではデジタル化が勢いを増しています。紙を使うことがエコではないと言われてしまう時代ですよね。そんな中あえて紙を使うこと、紙の魅力って江藤さんにとってどんなことですか?
江藤:ネット社会でメールを使うのが当たり前になって手紙なんて書かないですからね。普段はデジタルが圧倒的に便利だしいいと思います。でも、そっち一辺倒になっても趣がないというか。紙という手段を持っていないのはいやだなって思うんです。タイミングに合わせて手紙を出せるようなセンスっていいなって思いますね。例えば筆跡もそうですね。きれいな文字で丁寧に書かれていたり、そういうところからも気持ちが伝わります。印刷物もネットで気軽にできるようになりましたが、印刷物のすべてがいいとは思いません。これならわざわざ印刷しなくていいのに、メールでいいのにって思うこともあります。使うセンスが大切なのかな。どういう紙を選んで、どういう印刷方法でとか、手書きにするとか、どういう封筒を使うのかって。

江藤さんにとって魅力的な紙とは?
江藤:紙単体だと答えるのが難しいですね。印刷が載ったとき、加工されたときにその紙の魅力って引き立つと思うんです。ツルッとしている紙が悪いわけではないし、このペンで書いたらこの紙は走りやすいとかだったら、その紙を選ぶべきだと思います。こういう風なデザインでこういう風に見せたいって思ったらその通りにやるのがいいと思います。わざわざ活版にする必要もないんです。印刷技術が手段なのに目的になりすぎているものは、何でも活版でやればいいじゃんとか、何でもこの紙がいいよねって言われているからって。そういうのはあまり共感できないです。全部の相性を考えて作られている物はいいなって思います。普通のツルッとした紙にオフセットでもいい物はありますしね。
これから江藤さんがやりたいことはありますか?
江藤:あのインドの紙とかああいうことは大手のメーカーでは手を出しづらいでしょうし、紙自体は安いんですが、送料がかかると高くなっちゃうんですよね。紙ってまとまると重いですし。やはり紙は素材として好きなので、そういったことを自分たちで作って印刷も機械も持ってやれたらいいなと思いますね。たとえば自分たちでTシャツを回収して砕いて紙を作れたら楽しいなと思いますね。紙すきってすごく大変なんですよ。水は冷たいし、ゴミが入らないようにきれいにとったりして。手間をかければかけるほどきれいになるんですけれど、もう作る人もどんどんいなくなってきて、和紙の値段もすごく高くなってしまっているんです。だから売れなくて職人さんも少なくなってしまって。和紙の機械とか道具とか残っているはずなんです。なのでそういうのを引き取って活版再生展でやった時みたいな感じで実験的なことができたらいいなと思います。まだ模索中ですが。一般的にはNGとされている規格やずれいてるみたいなのでも面白じゃんって言ってくれる人もいると思うんですよね。
また新しい価値観で。
江藤:そうですね。大きな製紙メーカーができないことを個人レベルでできたらいいなと。

江藤公昭(パピエラボ店主)
2002年にランドスケーププロダクツにプロダクトデザイナーとして就職。2007年、紙にまつわるプロダクトを取り扱うショップ、パピエラボを設立。2010年1月に独立し、世界から集めた紙やそれにまつわるプロダクトを取り扱う。その他デザイン、印刷物のディレクションなどもおこなう。
Photo / Taro Hirano Text / Taku Takemura




